すいません。土曜に更新するといいながらできていません。
いいわけさせてもらいますと難航しています。
オチがつかない。気に入らない。文章がおかしいの三連続でのたうちまわっていますデス。
そんなことになっているので、ゲルツェン戦記の更新は、もう少しお待ちください。ほんと、すいませんの一言です。遙かのごとくデータ壊れたなどで連載中止なんてしませんし、これはしっかり書きあげますので。
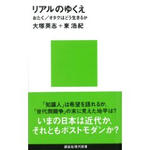
話は変わりますが、今、『リアルのゆくえ』という本を読んでいます。何度かこの日記でも書いた東浩紀さんと大塚英志さんの対談集で、まだ途中なのですが、けっこうおもしろいです。このふたりは、オタク論で有名なのですが、今回、私が読んで興味があったのは、作家論のところで作家のオリジナリティーってなによというところでした。詳しくは、本を買うなりして読んで見てくださいといいますが、(対談集なので書き方が独特で好き嫌いがあると思うので本屋で立ち読みすることをオススメします)作家のオリジナリティは固有性なのかというところをぐだぐだ語っていまして、そこに作品にまとまりがあるかないかが重要みたいにいっているところがあってそこがちょっと驚きました。「ほしのこえ」と「ブロッコリー」のことを中心に、というか「ブロッコリー」のデジキャラットに固有性があるのかいなかを二人が語っていますが、でじこは、確かにデータベースから萌え要素を選択して作られた、キャラであるが、ただの組み合わせに整合性をもちこんだ。その整合性を作った作家には固有性があると言っている。私としては、この整合性というのが気になってしまっています。独特な世界観やキャラクターをもっているのにいまひとつな話がよく不思議だなと思うことがあったのですが、整合性ということばを聞いてピタッといった気がしました。
そのほかにもおもしろい話が、いっぱいあるので是非とも買わないまでも立ち読みくらいはしてみてくださいな。
PR
